予防接種
予防接種で免疫をつけ、感染症にかからないように気をつけてあげましょう。
遅らせないで!子どもの予防接種
新型コロナウイルス対策が気になる保護者の方へ
予防接種名と接種方法
ヒブ(Hib)ワクチン
平成25年度から定期接種となりました。初回接種の年齢によって接種回数が異なりますので、注意して接種してください。
小児用肺炎球菌ワクチン
平成25年度から定期接種となりました。初回接種の年齢によって接種回数が異なりますので、注意して接種してください。
B型肝炎ワクチン
平成28年10月から定期接種となりました。B型肝炎ウイルスによる急性肝炎や、将来の肝硬変、肝がんを予防するためのワクチンです。
ロタウイルスワクチン
令和2年10月から定期接種になりました。ロタウイルス胃腸炎の重症化を予防するためのワクチンです。ワクチンは2種類あり、どちらも経口投与(飲むタイプ)の生ワクチンですが、ワクチンによって接種回数が異なりますのでご注意ください。
BCG
結核を予防するためのワクチンです。
五種混合ワクチン
五種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ)
令和6年4月から開始されました。五種混合は、ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブの5つの疾患を予防するためのワクチンです。
四種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)
平成24年11月から開始されました。四種混合は、ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオの4つの疾患を予防するためのワクチンです。
麻しん風しん混合ワクチン
麻しん(はしか)ウイルス及び風しんウイルスを弱毒化した混合の生ワクチンです。
水痘ワクチン
平成26年10月から定期接種となりました。水痘(水ぼうそう)を予防するためのワクチンです。
日本脳炎ワクチン
平成17年から日本脳炎予防接種の積極的な勧奨を差し控えていましたが、平成22年より接種機会を逃した方に対する接種機会の確保が図られることとなりました。
二種混合ワクチン(ジフテリア・破傷風)
乳幼児期に接種している「四種混合」または「三種混合」の第2期となり、ジフテリアと破傷風の免疫を上げるために必要となる接種です。
ヒトパピローマウイルスワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)
子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨については差し控えとなっていましたが、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから令和4年度より接種勧奨を再開する、と国から通知がありました。また、積極的勧奨の差し控え期間内に定期接種の機会を逃した方も対象となります。
接種医療機関
子どもの予防接種券の廃止と接種間隔の変更について
子どもの予防接種券の廃止について
これまで定期予防接種を受ける際は、医療機関に接種券を提出していただいていましたが、令和2年10月1日から不要になりました。
接種間隔の変更について
令和2年10月1日から、異なる種類のワクチンの接種間隔について、注射生ワクチンのつぎに注射生ワクチンを接種する場合は27日以上の間隔をあける制限は維持しつつ、それ以外のワクチンの組み合わせについては、一律の日数制限は設けないこととなりました。
それ以外のワクチンの組み合わせでは、前のワクチン接種からの間隔にかかわらず、つぎのワクチンの接種を受けることができるようになりました。
ただし、接種から数日間は、発熱や接種部位の腫脹(はれ)などが出ることがあります。
ルール上接種が可能な期間であっても、必ず、発熱や、接種部位の腫脹(はれ)がないこと、体調が良いことを確認し、かかりつけ医に相談のうえ、接種を受けてください。
なお、同じ種類のワクチンを複数回受ける場合、ワクチンごとに決められた間隔を守る必要があります。接種間隔につきましては、かかりつけ医とご相談ください。
- 注射生ワクチンとは、BCG、麻しん風しん混合、水痘、おたふくかぜ(任意接種)等のことです。
- 接種間隔は、接種した日の翌日から起算してください。
(注釈)新型コロナウイルスワクチンとの接種間隔は前後2週間あける必要があります。
接種券の廃止・接種間隔変更についての詳細はこちら (PDFファイル: 1.2MB)
小野市加東市の協力医療機関以外で定期予防接種を希望する方へ
小野市加東市の協力医療機関外で予防接種を希望する方へ(広域的予防接種のご案内)
里帰り出産やかかりつけ医等の理由により、小野市加東市の協力医療機関以外で定期予防接種を希望する場合、予防接種を受ける前に手続きが必要です。
申請なく予防接種を受けた場合は定期予防接種として取り扱いできないため、接種費用が自己負担となり、健康被害があった時の補償内容も変わります。ご注意ください。
県外の医療機関で予防接種を希望する方へ
県外の医療機関で予防接種を希望する方へ(償還払制度のご案内)
県外の医療機関で予防接種を希望される場合、接種前に申請していただく必要があります。申請なく接種した場合は、償還払いの対象となりませんのでご注意ください。
定期予防接種再接種費用助成事業
骨髄移植手術などで、接種済の定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断された方に対して、小児を対象とした定期予防接種の再接種費用を助成します。
予防接種健康被害救済制度
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害が起こることがあります。
極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
申請に必要となる手続き等については、小野市健康増進課にご相談ください。









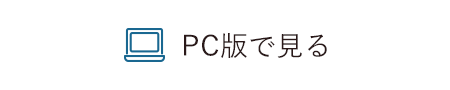
更新日:2024年04月01日