児童手当
直近の定時払についてお知らせします。
児童手当の概要
- 高校生年代までの児童を養育されている方(保護者)からの申請(認定請求)に基づき支給されます。
- 子の出生、他市からの転入や転出、離婚などによる受給者変更等は、出生日等異動事由が発生した日の翌日から起算して15日以内(15日目が、土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日の場合は、民法第140条から第142条の規定により、直後の開庁日が15日目となります)に申請が必要です。申請が遅れますと受給できるはずの手当月分が支給されません。
- 手当の支給開始月は申請の翌月分からです。ただし、月末生まれのお子さまの新規や増額申請等で翌月になった場合、申請書の受付日が閉庁日を含めて15日以内のときは、出生等異動事由発生日の翌月分(15日特例申請月分)から支給されます。
- 夫婦子ども世帯で、子の父または母のいずれが申請され受給者になられるかは、父母のうち生計を維持する程度の高い方(恒常的に収入の高い方)から申請していただくことになっています。
- 受給者である父または母が公務員になったときは、申請や手当の支給機関が勤務先(所属庁)となり、逆に退職や配属先異動等で公務員でなくなるときについても、15日以内に申請が必要となります。
【注意】
- 児童が、住民票を市内に置いたまま、1年以上の長期間にわたり海外の学校に在籍している場合など、生活の本拠としての実質を備えていないと認められる場合は、児童手当を支給することができません。生活の本拠がないことが後になって発覚した場合は、手当を返還していただく可能性がありますので、長期間にわたり海外に居住される場合は必ず住民票の異動の手続きおよび児童手当の「受給事由消滅届」等の提出をお願いします。
- 両親のうち、一方だけが海外に居住する場合は、他方の国内で児童を養育する方が受給者となります。受給者が国外に出国される場合は、受給者の方に「受給事由消滅届」を提出していただくとともに、国内で養育される方に「認定請求書」を提出していただく必要があります。
手当受給者
- 児童を監護し、かつ、生計を同じくする父または母(生計を維持する程度の高い方)
- 上記以外で、児童を監護し、かつ生計を維持されている方(祖父母等の養育者等)
- 支給対象となる児童は、国内に居住している場合に限られます
(留学中の場合は除く)。 - 父母が別居(単身赴任を除く)の場合、児童と同居している保護者の方(申立書類要)に支給となります。
- 児童が児童養護施設等に入所している場合は、父又は母等への支給とならず、施設の設置者等への支給となります(施設等とは保育所などの通所や児童が保護者とともに入所する場合を除きます)。
- 未成年後見人や、父母がともに国外居住の場合は父母が指定する者に、手当が支給されます。
支給額
| 児童の年齢 | 支給月額 (1人当たりの金額) |
|
|---|---|---|
| 3才未満の児童(3才誕生月分まで) |
|
|
| 3才(誕生日翌月分)から高校生年代(年度末3月分)まで |
|
|
- 注釈1:3歳未満の児童とは誕生日の属する月分まで該当し、誕生日の翌月分から3歳以上の児童に該当することになります。
- 注釈2:第1子、第2子などのカウントは、満22歳の年度末(一般には大学卒業)までの児童を上から年齢順に数えた児童順呼称です。
所得制限
令和6年10月分から所得制限が撤廃されました。
支給日・支給方法
| 支給日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 令和7年4月15日(火曜) | 2月分~3月分 |
| 6月13日(金曜) | 4月分~5月分 |
| 8月15日(金曜) | 6月分~7月分 |
| 10月15日(水曜) | 8月分~9月分 |
| 12月15日(月曜) | 10月分~11月分 |
| 令和8年2月13日(金曜) | 12月分~1月分 |
- 2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回、2か月分ずつ(支給月の前月分まで)を指定の受給者名義の口座に振込みます。
- 支給月の15日(支給日が、土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その前の平日)です。
大学生年代の子を多子加算のカウント対象とするには
申請様式
- 認定請求書(PDFファイル:156.2KB):第1子出生や転入などで新規に申請するとき
- 額改定認定請求書(PDFファイル:116.1KB):受給者に第2子以降の子の出産などで監護する児童の人数に増減があったとき
- 受給事由消滅届(PDFファイル:107.9KB):他市転出や児童の監護をしなくなったとき
- 別居監護申立書(PDFファイル:46.5KB):別居している児童を監護されている方
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:77KB):18歳年度末経過後22歳年度末までの子を含めて養育する子が3人以上いるとき
- 受給資格に係る申立書(PDFファイル:97.9KB):離婚協議中などで児童と同居されている方が申請するとき
- 氏名・住所等変更届(PDFファイル:104.9KB):受給者や児童の住所・氏名に変更があったとき
- 個人番号変更等申出書(PDFファイル:63.1KB):受給者等のマイナンバーが変更されたときや、婚姻・離婚等で配偶者等に変更があったとき
- 手当振込金融機関口座指定・変更届(PDFファイル:60.1KB):児童手当の振込口座を指定又は登録口座の変更を届け出るとき
- 父母指定者指定届(PDFファイル:73.6KB):父母ともが海外にいて、その児童を養育されている方
- 未支払児童手当請求書(PDFファイル:84.3KB):受給者が亡くなられた場合
- その他、海外に留学している児童の申立書や未成年後見人申立書などは市窓口に備えています。
- 情報連携ができない方につきましては、添付書類の提出をお願いします。









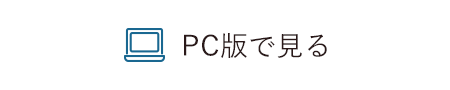
更新日:2025年11月07日