市長施政方針
令和7年2月 第452回小野市議会(定例会)
はじめに
第452回市議会定例会の開会にあたり、令和7年度当初予算をはじめ、重要案件の慎重なるご審議をお願い申し上げますとともに、市政に取り組む所信の一端を申し述べ、議員各位並びに市民の皆様方のご理解とご支援を賜りたいと存じます。
胆力が試される小野市の基盤づくり
昨年は、日経平均株価も最高値を更新するなど、いよいよ「失われた30年」から脱却し、物価上昇と「金利のある世界」が現実となり、日銀の政策金利がリーマン危機前の2008年10月以来となる0.5%に引き上げられました。2025年度の政府経済見通しでは、経済成長が4年ぶりに加速し、GDPの実質成長率は1.2%になると見込まれるなど、日本の景気は緩やかな回復が続くと見られております。
しかしながら、政策金利の引上げによる国の財政悪化や企業の資金調達コスト増などの金利高騰のリスクが指摘されはじめたほか、円安による物価上昇もあってか、2024年の実質賃金は前年比マイナス0.2%と3年連続でマイナスが続いていることや、すでに世帯の半数以上が、65歳以上の方がいる世帯であることから、賃上げなどの企業努力だけでは限界があり、高齢化による成長力の低下が経済成長の足かせとなっていることも事実であります。
そのため、豊かさの目安とされる1人当たりの名目GDP(2023年)では、OECD加盟国38か国中、日本は33,849ドルで22位であり、韓国の35,563ドルを下回っております。G7においてもイタリアの39,003ドルを下回り、2年連続最下位という現実からすれば、日本は確実に貧しい国になっていると言わざるを得ません。
世界を見渡せば、深刻な不動産不況を背景とした中国経済の不透明感から、日本企業は、海外事業展開における北米依存を強めてまいりました。しかしながら、米国ではトランプ政権が発足したことにより、日本を含む海外企業の事業展開そのものを妨げる保護主義的な動きが強まる可能性があることから、企業のグローバル経営は難度を増しております。
国内では、戦後最大級の国内製造業同士の経営統合と言われる「ホンダ」と「日産」との経営統合協議は、業績面から対等な経営統合を巡る溝が埋まらず、経営統合協議が打ち切られたものの、成長に必要な巨額投資に見合う経営基盤の再構築が求められる変革期に入ったことを象徴する出来事であると考えております。
さらには、市場から自社の株式を買い戻し、1株当たりの利益を引き上げて株高を促す「自社株買い」の金額が、2024年は過去最高となり、日本企業のM&Aも、1985年以降で最多となったと報じられております。企業は、今や日本株の主要な買い手であり、2025年もこの流れが続くものと想定されていることから、経営基盤の再構築に加え、株価を意識した経営も、重視される時代となっております。
日本の景気は、非製造業がけん引している一方で、製造業の不調が景気回復の重荷とも言われておりますが、これまで、日本企業は、人口が増え、中間層が拡大する新興国を消費地や人材供給源として、自らの成長につなげてきました。しかしながら、海外事業展開の難度が増している状況の中にあって、株価や株主還元を意識した経営を行いながら、グローバルサウスとして力をつけてきている新興国とうまく協調し、企業の価値創造力をいかに高めるのかという戦略が、企業の命運を左右するようになっております。
その一方、政治の世界において、米国は、これまで民主主義と自由競争、そして資本主義のダイナミズムで世界の覇権国になったものの、製造業の衰退とともに経済格差が広がり、2022年半ばにインフレ率が9%超となり、所得格差やインフレといった生活者の不満に民主主義政治が対処しきれず、自由競争が全体の成長につながることなく勝者と敗者の溝を大きくしていると言われております。
中間層の衰退が、中道政治の後退につながり、与野党が中傷し合うだけの姿は、民主主義政治へのさらなる不信感を強め、国民の分断が進み、独裁色の強い為政者が生まれやすくなっていることから、世界の民主主義が後退し、混迷する世界が幕を開けたと言われております。特にSNSの普及により、「争点対立」から「感情対立」へと民衆が誘導され、極論の発信が、均衡点を移動させてしまうという「世論ハック」が懸念されるようになってまいりました。
さて、我々、地方自治体においても「静かな有事」と呼ばれる人口減少と超高齢社会進展の真っ只中にあって、「地方創生2.0」と銘打った新たな地方創生の取組が、石破総理のもとスタートしております。そのスタートにあたり、これまで10年間の地方創生を振り返った総括では「人口減少や、東京圏への一極集中の流れを変えるまでには至らなかった」とされた上での「地方創生2.0」であります。
地方自治体は、地方創生法に基づき、地方版総合戦略を策定する努力義務を負っておりますが、この戦略は、人口減少を食い止めるために、子育て支援などの出生率向上策、Uターン、Iターンなどの移住促進策、雇用創出やインバウンドなどによる経済活性化策などに注力するという内容で、どれも判で押したような同じ内容となっているのが現状であります。
産業構造の転換をはじめ、民主主義そのものの後退が叫ばれている混迷する世界の中で、我々、地方自治体だけが、国からの指示や交付金を当てにして、前例踏襲型の受動的な行政経営を行っているだけでは、勝ち残っていくどころか、生き残っていくこともできません。
このような混迷する時代の転換期だからこそ、企業が経営基盤の再構築を行い、成長投資を行う必要があるのと同じように、目先の感情に振り回されることなく、将来を洞察しながら、小野市の将来ビジョンを明確にし、その選択が正しいことを市民の皆様に説明、納得してもらえる「胆力のある投資」や「行政経営基盤の再構築」が求められているのであり、それが次の小野市発展の基礎となるものと考えております。
今年は、「大阪・関西万博」の開幕の年であります。55年前の1970年に開催された大阪万博の際に、今や「鴻海(ホンハイ)」の傘下となったシャープでありますが、万博へのパビリオン出展を取りやめ、その資金も活用して奈良県天理市に「総合開発センター」を建設し、将来の会社発展を方向づける総合エレクトロニクス分野の事業を加速させました。
それは後に「千里より天理への英断」と呼ばれることになり、その後の同社の技術開発や人材育成の拠点となり、同社発展の礎となったということであります。当時は、テレビの対米輸出ダンピング提訴など、国内外に様々な問題を抱えており、それに追い打ちをかける「ニクソンショック」と呼ばれる経済政策により、株価は一時暴落、輸出が低下して景気が停滞した時期であります。
我が国は、明治維新以来、概ね40年サイクルで上昇期と下降期を描いております。すなわち、1865年から1905年までの富国強兵、日露戦争勝利までの上昇期とその後の第二次世界大戦敗戦に至る1945年までの下降期、次に戦後民主主義から高度経済成長、プラザ合意にいたる1985年までの上昇期とその後のバブル崩壊後の下降期であるいわゆる「失われた30年」の期間であります。
昭和100年に当たる今年は、この40年サイクルに従えば、いよいよバブル崩壊後の下降期から上昇期へと転換する年であります。この上昇期の波に乗れるか否かは、受動的に自らを順応させるだけではなく、むしろ積極的に新しいものを果敢に作り上げていく強い意思があってこそ成し得ることであり、小野市は、その基本理念のもと、飽くなき挑戦者であり続けるために、後に「英断」であったと言われるように、令和7年度も引き続き、積極的に事業を展開してまいります。
その基本理念となるのが、四半世紀に及ぶ市政運営において、決してぶれることのなかった「行政も経営」であり、「より高度でより高品質なサービスをいかに低コストで提供するか」を追求することであります。
また、そのための「行政経営4つの柱」、すなわち、
1つに、市役所は市内最大のサービス産業の拠点であり、市民=顧客と捉えた「顧客満足度志向(CS志向)の徹底」、
2つに、何をやっているのかではなく、何をなし得たかを問う「成果主義」、
3つに、画一的横並びの仲良しクラブから脱却し、ここにしかない小野らしさ、持ち味を追求する「オンリーワン」、
そして4つに、言われてからやるのではなく言われる前にやる「後手から先手管理への転換」
を基軸に市政運営を行うという姿勢は、何ら変わるものではありません。
新年度予算の主な施策
令和7年度は、総額236億1千万円の予算額としております。昨年度と比較しますと、3億5千万円、1.5%の増としており、10年連続200億円超えの積極型予算であります。
国の補正予算の関係で3月補正予算に前倒しした15億2千万円と合わせますと251億3千万円となり、250億円超えは、令和元年度の新庁舎建設時以来の“超積極型予算”であります。
歳入の主軸となる市税収入は、昨年度実施された「個人住民税の定額減税の廃止」だけでなく、「ひょうご小野産業団地」の稼働に伴う償却資産などの固定資産税や法人市民税などの増加に伴い、対前年度当初予算比で4億8千万円の増となり、過去最高となる79億3千万円を見込んでおります。
前倒しした補正予算と合わせても基金からの繰入金は、対前年度当初予算比3千万円減の17億1千万円、市債発行額については、対前年度当初予算比6億5千万円増の22億1千万円となり、税収増を踏まえ、“超積極型予算”でありながらも、健全な財政基盤を堅持する予算としております。
時代の転換年となるとも言える令和7年度予算の重点項目は、大きく「4つ」としております。すなわち、
1つには、「市民力を活かす地域づくりの推進」
2つには、「子育て支援・教育環境の充実」
3つには、「安全・安心に暮らせるまちづくりの推進」
4つには、「未来ひろがるまちの創造」であります。
≪1. 市民力を活かす地域づくりの推進≫
まず、1つ目の重点項目である「市民力を活かす地域づくりの推進」についてであります。
地域力の要となる自治会活動に対して、令和6年度に、市と自治会との連絡手段の簡素化を図るため「LINE WORKS」を導入したところです。引き続き、自治会業務の負担軽減、効率化のため、意欲のある自治会に対し、従来の「地域のきずなづくり支援事業」と併せ、電子回覧板の導入などデジタル化の支援を継続してまいります。
また、多様な地域づくり活動を支援し、持続可能なコミュニティ形成の実現に取り組む市内6地区の「地域コミュニティ活動推進補助」についても継続した支援を行うとともに、地産地消の推進と併せ、高齢者等への就労場所の提供や独居世帯への食事支援などの機能を有している「コミュニティレストラン」を支援してまいります。
地域住民が主体となって運営し、隠れ家のような憩いの場となっている「鍬溪温泉きすみのの郷」の活動支援も継続していくほか、今後、急激に高齢化が進む下東条地区において、同じく地域住民が主体となって買い物支援や地域の絆づくりを担っている下東条地区の公設コンビニ「ふれあいマート」への支援も継続してまいります。
誰もがいつまでも地域でいきいきと活動できるよう、令和7年度で開始から5年目を迎える、後期高齢者に対するフレイル予防事業では、高齢者の生活習慣病の重症化予防のために、市の保健師及び管理栄養士が、健康状態を把握できていない方に対し、戸別訪問を行っていくほか、「いきいき100歳体操」においてフレイル予防に関する教育講話を行うことで、高齢者の生活機能低下の防止を推進してまいります。
関西内陸部最大規模のイベントである「小野まつり」については、創意工夫による新たな「まつりの姿への創造」を期待しつつ、市民と行政との「参画と協働」が目に見える形の「まつり」として、元気な小野市を発信してまいります。さらに、今年で12回目を迎え、「冬のおの恋」として定着した「小野ハーフマラソン」においても、市民のボランティアマインドを結集し、全国から多数集まったランナーを「おもてなし」の心で出迎え、元気な小野市を発信してまいります。
「小野市詩歌文学賞・短歌フォーラム」では、短歌部門選考委員の「永田和宏先生」「小島ゆかり先生」に加え、昨年度から俳句部門の選考委員に「高野ムツオ先生」をお迎えし、“継続し続ける”という理念のもと、無形の財産を築き上げるべく「短歌のまち小野」を全国に発信してまいります。
平成17年3月にオープンし、この3月20日に開館20周年を迎える「うるおい交流館エクラ」では、今年の1月に、入館者数が500万人を超え、市民活動の拠点として多くの方々にご利用いただいております。令和5年度から計画的に改修事業を進めており、令和7年度も空調設備改修工事、エクラホール内の照明設備更新工事などに取り組み、引き続き、市民活動活性化の拠点施設としての役割を果たしてまいります。
今月に入館者数が700万人に到達し、年間35万人の方にご利用いただいている「白雲谷温泉ゆぴか」においては、防水塗装、照明設備などについて計画的に改修し、適切な施設維持管理を継続することで、快適さとやすらぎが感じられる空間を提供し続けてまいります。
また、近年、需要が高まっているスタートアップを支援し、同時に小野商店街の空き店舗の有効活用が図られるよう、店舗の「所有者」及び「出店者」に対し、それぞれ店舗改修費等の2分の1を助成する制度を継続していくほか、近隣住民が市内事業者を知るきっかけ作りの場として、「おの恋楽市楽座」を開催し、小野市の商工業の振興と地域経済の活性化を図ってまいります。
その他にも、地域活性化を更に推進するため、インパクトのある情報発信を展開し、「ふるさと納税制度」も活用しながら、効果的な観光プロモーションに取り組んでまいります。
≪2. 子育て支援・教育環境の充実≫
次に、2つ目の重点項目である「子育て支援・教育環境の充実」についてであります。
平成28年7月から、県内でいち早く開始した「高校3年生までの医療費の所得制限なしでの完全無料化」は、令和6年度時点では、県内の21市町、約51%の自治体にまで広がり、小野市はその先駆者としての役割を果たしてまいりました。
加えて、妊娠・出産時にそれぞれ5万円を支給する「妊娠支援給付金事業」についても、引き続き実施していくほか、妊娠から出産にかけて母子の健康を守り、安心して出産が迎えられるよう、妊婦健康診査費の一部助成額について、2万円増額し、令和7年度から12万円とし、若い世代の経済的負担を軽減してまいります。
保育環境の充実を図るため、新たに市内保育所における園児の登園管理などのデジタル化支援に着手するとともに、ニーズが高まっている学童保育(アフタースクール)については、小野東小学校敷地内に新たな教室を建設するなど環境整備を行い、待機児童対策に取り組んでまいります。
市内保育所の「認定こども園化」についても、本年4月には8園目となる「小野ひまわりこども園」が誕生する予定であり、「育ヶ丘保育園」では、安全対策として老朽園舎の改修工事に着手いたします。
次に、教育環境の充実については、超スマート社会(Society5.0)を豊かに生き、自ら未来を切り拓く人づくりを目指した「おの夢と希望の教育」の更なる推進を目指し、「NEXT GIGA(ネクスト ギガ)」、すなわちGIGAスクール構想の第2段階として、1人1台端末の更新や新たな学習支援ソフトの導入など、さらに進化したICT教育環境の整備に着手いたします。
また、今年度は、「大阪・関西万博」が開催されることから、未来を担う子どもたちに『特別な学びの場』を提供するため、児童・生徒に対し、「大阪・関西万博」への参加旅費を支援し、体験活動の充実を図ることとしております。
さらに、児童・生徒の熱中症対策と避難所機能の強化を目的とした「学校体育館空調整備」については、いよいよ工事に着手し、中学校から先行して整備を行い、市内すべての学校体育館への空調整備に取り組んでまいります。
すでに着手しております「おの幼稚園」整備工事については、令和8年1月の完成に向け、建設工事が本格化いたします。「おの幼稚園」では、小野市教育行政顧問である東北大学川島隆太教授の『脳科学理論』に基づいた“幼児教育の実践”の場として、隣接する小学校との連携や親子の愛着形成を図る取組を強化するとともに、天然芝の園庭など、魅力ある屋外教育環境を整備いたします。
学校施設の長寿命化対策については、旭丘中学校において、昨年11月に完成した校舎に引き続き、体育館建替工事に着手するとともに、河合中学校の長寿命化事業に向けた基本・実施設計に取り組んでまいります。
また、各学校施設においては、教室の空調設備の更新、教室照明のLED化、エレベーターの設置、インターホンの整備など、質の高い学習環境の整備を積極的かつ計画的に進めてまいります。スポーツ施設においても、匠台公園体育館アクトの空調改修や床の美装化を進め、市民のスポーツ活動を支援してまいります。
≪3. 安全・安心に暮らせるまちづくりの推進≫
次に、3つ目の重点項目である「安全・安心に暮らせるまちづくりの推進」についてであります。
平成16年1月から運行を開始した、コミュニティバス「らんらんバス」は、現在、9台、11ルート、175箇所の停留所を設置し運行しております。令和6年度の年間利用者数は20万人を超える見込みで、市内高齢者の移動手段となっているだけではなく、通勤、通学の手段としても利用されており、今や市民にとって、欠かすことのできないものとなっております。
さらに、「らんらんタクシー」は、定時定路線の「らんらんバス」を補完する施策として、令和4年10月から運行を開始しているところですが、利用登録者数が既に1,300人を超え、高齢者の買い物や通院などの多様な移動ニーズに応える交通手段としてご利用いただいております。引き続き、超高齢社会のニーズに沿い運行を継続してまいります。
また、「8050問題」をはじめ、複雑化・複合化する福祉支援ニーズに対し、既存の縦割り対応ではなく、分野横断型の包括的な相談支援を行うため、「重層的支援体制」の整備に引き続き取り組むとともに、「ひきこもり支援」として、新たに予約制の相談や講演会等を実施し、ひきこもり状態にある方や家族の方への支援に取り組んでまいります。
あわせて、障がい者や家族の方が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、これまで障がい者の総合的・専門的相談窓口であった「障がい者地域生活・相談支援センター」を、地域における相談支援の中核を担う「基幹相談支援センター」として機能強化し、相談支援と地域生活支援体制の充実を図ってまいります。
また、予防接種法の改正により、帯状疱疹ワクチンは、令和7年度から任意接種から定期予防接種となっております。そこで、小野市では5年間の経過措置として「65歳以上の方全員」を対象に、接種を実施することにしております。同時に、その助成費についても拡充し、令和7年度からは生ワクチン接種1回につき4,000円、不活化ワクチン接種1回につき10,000円(2回接種)の助成を行い、市民の方の健康増進に寄与することにしております。
次に、平成16年から開始した「安全安心パトロール」は、隊員が警察官OBならではのプロの視点で、犯罪が発生しやすい場所における警戒活動や環境美化活動、通学路における児童・生徒の見守り、交通安全教室など、市民の防犯・交通安全意識を高める活動を展開しております。
市内の刑法犯認知件数は、ピーク時の平成13年には1,473件だったものが、令和6年には271件と82%も減少するなど、地域全体で犯罪等を未然に防ぐための取組が、“見える成果”として表れ、市民の体感治安の向上に寄与しているものと考えております。
「安全安心パトロール」に加え、防犯カメラや防犯灯の設置、防犯灯のLED化、警察と連携して身近な防犯情報を配信する「安全安心メール」などにより、まちの防犯機能、防犯意識を高め、市民が安全で安心して暮らせるまちづくりに引き続き取り組んでまいります。
また、令和6年度から令和8年度までの3年間を集中取組期間としている、ごみステーションの整備と美化については、自治会への整備経費の助成額を上限30万円、補助率を2分の1に引き上げており、ガラスびん回収用ドラム缶についても、希望する自治会に対しては、軽量で景観に配慮したプラスチック製のものへの交換を無償で進めております。
令和6年度には、市内全自治会の半数以上からドラム缶の交換申請があったところであり、令和7年度においても、ごみステーションの整備と美化を推進し、ごみ出しに対する負担軽減と意識改革に取り組んでまいります。
30年以内に80%という高い確率で発生すると言われている「南海トラフ巨大地震」に対し、備蓄している防災資機材の棚卸を踏まえ、その充実を加速させるほか、災害時の避難所における生活環境、防災意識の向上を目的に、移動式トイレトレーラーを整備することにしております。
資機材等の整備だけではなく、地域防災の担い手である消防団員の処遇改善を行い、人材面においても備えを加速させていくとともに、地域防災の中核を担う西分団特設部のポンプ車両の更新整備を行い、消防団組織の充実、強化を図ってまいります。
また、救急体制の充実として、「救急安心センター事業(#7119)」を開始いたします。後期高齢者の増加による救急需要の増大と、働き方改革による医師等の確保が課題となる中、救急出動件数は全国的にも増加傾向にあることから、市民が救急車を呼ぶべきか判断に悩む場合に、専門職が電話相談に応じる「救急安心センター事業(#7119)」による相談体制を構築し、救急車の適正利用につなげてまいります。
その他にも、住宅等への倒木被害から市民の生命・財産を守るため、森林環境譲与税を活用して、危険木の伐採、撤去及び処分に要する経費の一部を助成し、安全安心で住みよいまちづくりを支援していくほか、近年の集中豪雨による浸水被害状況をリアルタイムで面的に把握できる国土交通省による「ワンコイン浸水センサ」の実証事業に取り組んでまいります。
次に、国土交通省との共同事業である「かわまちづくり事業」でありますが、加古川左岸、新大河橋南側の河川空間を活用し、平常時は「おの桜づつみ回廊」と一体利用できるレクリエーション機能を有し、地域の交流やにぎわい創出拠点として、災害時には加古川中流域における防災ステーション機能を有した緊急活動拠点となる「MIZBE(ミズベ)ステーション」の整備を進めております。令和7年度は、国土交通省が実施する造成工事の完了後、市が施設整備に着手することとしており、令和9年の完成を目指しております。
ため池の安全確保については、42.6haに及ぶ農地を擁し、重要な地域のかんがい用水源である「八ケ池」は、引き続き、耐震化工事を実施し、令和11年度の完成を目指してまいります。あわせて、市内に農業用ため池は308箇所ありますが、近年の集中豪雨により決壊すれば下流に影響のある防災重点農業用ため池197箇所のうち、利用実態のないものについては、順次、廃止工事を実施してまいります。
次に、道路改良事業についてであります。まず、多くの児童・生徒が通学路として利用する葉多町から下大部町までの「片山高田線道路改良事業」については、「第1工区」に引き続き、下大部町から片山町までの「第2工区」の整備を順次進めており、令和7年度中に整備が完了する予定であります。
消防車等の緊急車両の通行が困難である集落内の狭小な主要道路である池尻町内の市道4309号線や河合中町内の市道2148号線については、拡幅工事を継続し、安全かつ円滑に通行できる道路環境を整備していくとともに、老朽化が進み、自治会からも多くの要望をいただいている生活道路の舗装修繕を計画的に実施し、安全性の向上を図ってまいります。
老朽化する橋梁が増加する中、5年毎の点検結果を反映した「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、計画的かつ効果的に補修を実施し、長寿命化を図るとともに、近年頻発する豪雨に備え、河川に堆積した土砂の撤去等により、市が管理する河川を適切に維持管理し、災害の未然防止策を講じてまいります。
≪4. 未来ひろがるまちの創造≫
最後に、4つ目の重点項目である「未来ひろがるまちの創造」についてであります。
令和2年4月に「小野希望の丘陸上競技場」をオープンさせた「浄谷黒川丘陵地」の利活用については、現在、小野加東加西環境施設事務組合による3市の生活基盤を支える「新ごみ処理施設」の整備事業が進捗しております。今後は、当該丘陵地における多角的な土地利用を目指し、小野市の将来を支える最重要拠点として、産業団地整備の可能性について本格的に調査を進めてまいります。
先ほど申し上げました「新ごみ処理施設」につきましては、令和6年度から整備に向けた体制を構築しているところですが、「NIMBY(ニンビー)な迷惑施設」という従来の概念から脱却した、人が集い、憩う「地域に親しまれ、開かれた施設」という基本理念の実現に向け、令和7年度からは基本計画の策定に着手いたします。人口減少が加速していく中において、広域化の取組は避けて通れないものであり、加東市、加西市、そして小野市が一体となって本事業を進めてまいります。
また、図書館東側区域においては、シビックゾーンの活気とにぎわいが持続するよう、商業施設の立地による新たな市街地開発を目指し、引き続き、官民連携の取組を進めてまいります。
令和7年には、国道2号バイパスと国道175号とを結ぶ「東播磨道」が全線開通し、さらには「東播磨道」が接続する国道175号「市場東交差点」付近の「6車線化」も完成する予定となっております。加えて、「ひょうご小野産業団地」内を南北に縦断し、山田町を経由して小野ニュータウンへと抜ける「新都市南北線」の整備も、令和7年度の完成に向け順調に進捗しております。
「三木スマートインターチェンジ」の整備とも併せ、交通渋滞の緩和だけでなく、東播磨地域と北播磨地域との連携強化による雇用の創出、医療ネットワークの飛躍的な向上、沿道における開発の促進など、小野市だけでなく北播磨地域全体のポテンシャルを飛躍させる事業が完成し、まさに地方創生の真価を問う基盤が整いますので、今後、これらをどう活かしていくかが我々に問われることになると考えております。
次に、公共施設の最適化に向け、公園が受け持つ機能や役割を再検証し、既存公園の再編や管理の効率化を図るため、持続可能で次世代につながる公園のリニューアル計画を策定してまいります。貴重な歴史遺産であり、地域のシンボルとして次世代につないでいくべき、金つるべ城跡広場では、老朽化した木橋を更新することにしております。
「北播磨総合医療センター」については、開院から12年目を迎え、名実ともに北播磨医療圏域の「基幹病院」に成長しております。急性期の医療を担い、高度で、より質の高い医療を目指しつつ、地域の関係機関との連携を深め、北播磨地域で完結する切れ目のない医療の提供に努めております。
コロナ禍に起因する2病棟の閉鎖後、減少した看護師の確保に、精力的に取り組み、昨年の3月には5階西病棟を再開し、現在の実稼働病床は352床まで回復しております。一方で、人事院勧告に伴う給与アップや急激な物価上昇は、アフターコロナにおける病院経営をより深刻化させているのも事実であり、企業団自体も、増収や経費削減に努めておりますが、その取組にも限界があることから、小野市としては、三木市と協調した追加支援が必要と判断しており、国が定める繰出基準の範囲内において、負担金の増額予算を計上しております。
最後に行政改革に関する取組についてであります。小野市では、他市に先駆けて平成12年4月より、毎週土曜日、市民課窓口を開庁し、住民票等の証明書の発行を行ってまいりました。この取組は、マイナンバーカードの普及促進にあたっても効果を発揮し、令和6年12月末時点で、小野市民のマイナンバーカードの取得率は、約84%に達しております。現在は、市民の利便性を高めるため、コンビニエンスストアにおける住民票等の証明手数料を、県内最低金額の100円に引き下げたことで、約5割の方が市役所に来庁せず証明書を取得されるようになっております。
令和6年12月から健康保険証の新規発行が停止され、「マイナンバーカード」を利用した「マイナ保険証」の利用が始まる中、各種証明証については、「市役所に行かずともマイナンバーカードで取得」という新たな常識を醸成するため、令和6年度末で土曜窓口を終了し、市民の意識改革とマイナンバーカードを活用した行政手続の簡素化に取り組んでまいります。
このほか、「地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化」が進められておりますが、令和7年度末を目標として、ガバメントクラウドを活用した標準準拠システムへの移行を進めているほか、生成AIの業務利用やRPAによる業務の自動化を図り、DX推進を一段と加速させ、市民サービスの質の向上と行政運営の効率化に取り組んでまいります。
予算総額と健全な財政運営
以上、令和7年度予算は、一般会計236億1千万円、特別会計105億7千万円、企業会計56億6千万円で、総額を398億4千万円としております。
財政状況については、積極的に様々な事業を実施する一方で、行政運営を効率的に進めてきた結果、基金、いわゆる預金の残高は、令和7年度末において、約80億円の基金残高を確保できる見込みであり、独自財政指標のガイドラインである70億円を堅持できる見込みであります。
一方、借金にあたる地方債残高は、学校施設の長寿命化改良工事や新都市南北線の整備などによって、令和7年度末に204億円となる見込みでありますが、そのうち約7割にあたる133億円は、後年度に国から補填されるため、市の実質負担は約3割の71億円であります。
また、次世代が負担すべき借金をはかる「将来負担比率」は、決算が確定した令和5年度において「マイナス1.5%」であり、引き続き令和7年度も県内市平均を下回る見込みで、将来に「ツケ」を回すことなく、健全財政を堅持できるものと考えております。
今期定例会には、一般会計予算案をはじめ、24件の議案を提出しております。細部につきましては、各担当者が説明いたしますので、慎重にご審議のうえ、ご決定いただきますようお願い申し上げます。
おわりに
世界に目を転じれば、世界の企業の時価総額において上位100社の中には、トヨタ自動車を除いて日本企業の姿はありません。30年ほど前には日本企業が上位に名を連ねていたことからすれば、世界の中で、半導体、家電など、日本企業が得意としてきた分野で、海外の安価な商品に押され、撤退や縮小を余儀なくされてきたことが、「失われた30年」を象徴しております。
今や世界では、AI投資がかつてない規模で進もうとしております。世界の上位に位置する企業は、この30年の間に「新たな価値を創造」してきた企業であり、我々の既成概念を超えた発想で、世界を変えてきた企業であります。イノベーションは、先行する製品、サービスの価格破壊に伴って普及していくものであり、世界を変えてきた企業は、それをまさに具現化してきた企業であります。
我々、地方自治体においても、人口減少時代にもかかわらず、個々人という人口のパイを奪い合い、囲い込もうという発想から脱却しなければ、真の地方創生は実現困難であり、地域が活性化し、将来に飛躍し続けることはできません。
「未来」とは、過去と現在とを結んだ延長線上にあるのではなく、既成概念を打ち破った先にあるのであり、「明日」は今日の延長であるという錯覚から脱却しなければなりません。「未来」を生き抜くには、変容、変転に順応することは必然であり、「新たな価値創造力」を高めていくことが、これからの小野市を創造し続けることにつながるものであります。
そのためには、“今まではこうであったという前例を踏襲することなかれ、かくあらねばならんという固定観念に捉われることなかれ”と、自らに課し、先人から受け継いだ“我がまち小野”の希望ある未来を切り拓いていくことが、我々に課せられた責務であり、使命であります。
「政治とは無限の理想への果てしなき挑戦」であります。
「行政も経営」という、いつまでも変化しない本質の中に、新しく変化を重ねていくものを取り入れ、絶えず変わり続ける“不易流行”のごとく、世の中の変化に柔軟に、かつ、ポジティブに挑戦し続ける挑戦者として、粉骨砕身、邁進してまいりますので、皆様のより一層のご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。









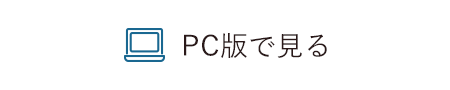
更新日:2025年02月26日