後期高齢者医療保険料(令和7年度)
保険料は被保険者全員が納めます
国民健康保険では、世帯単位で計算して世帯主がまとめて国民健康保険税を納付したり、健康保険組合などの被扶養者では保険料負担がなかったりしますが、後期高齢者医療制度では被保険者全員が保険料を納めることになります。
保険料の納付方法
年金が年額18万円以上の方の場合は、保険料は年金からの天引き(特別徴収)となります。それ以外の場合は個別に口座振替または納付書で納めます(普通徴収)。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引き対象にはなりません。
保険料の決まり方
令和7年度の保険料は、被保険者1人当たりいくらと決められる「均等割額」と、被保険者の令和6年中の所得に応じて決められる「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。均等割額と所得割率は、広域連合ごとに決められ、原則として県内で統一となります。 (2年ごとに見直されます。)
保険料額(年額)(上限80万円) = 均等割額:52,791円 + 所得割額:(総所得金額等-基礎控除額43万円)×11.24%
※総所得金額等とは収入額から次の控除額を引いた金額です。(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費。ただし、所得控除額(社会保険料控除額、扶養控除額等)は含みません。)
※合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。
所得の低い方の軽減措置
所得が低い世帯の方は、保険料の均等割額が世帯の所得水準にあわせて、つぎの表のとおり軽減されます。
| 総所得金額(世帯内の被保険者全員+世帯主)が次の基準額以下の世帯 | 軽減割合(軽減後の均等割額:年額) |
| 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者-1) | 7割(15,837円) |
| 基礎控除額(43万円)+30.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者-1) | 5割(26,395円) |
| 基礎控除額(43万円)+56万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者-1) | 2割(42,232円) |
※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。(年金特別控除)
※年金・給与所得者とは、同一世帯内の被保険者と世帯主のうち給与所得または公的年金等所得およびその両方がある者をいいます。
被用者保険の被扶養者の軽減措置
制度に加入する前日に、会社の健康保険等の被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額はかからず、資格取得後2年間は均等割額が5割軽減され、年額26,395円となります。なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。
※被扶養者であった方でも、世帯の所得が低い方の軽減を受けることができます。ただし、両方受けることができる場合は、軽減割合の高い方が適用されます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 福祉高齢医療係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1469
ファックス:0794-63-7674
メールフォームによるお問い合わせ









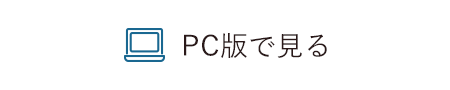
更新日:2025年05月20日