ダニ媒介感染症にご注意ください
ダニがウイルスや細菌などの病原体を保有している場合、咬まれた人が病気を発症することがあり、国内ではマダニ類による日本紅斑熱、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、ツツガムシ類によるつつが虫病などが知られています。県内では、近年、春から秋にかけて日本紅斑熱の患者数が増加傾向で、ダニに咬まれたと推定される感染地も拡大傾向にあります。
ダニ媒介脳炎や重症熱性血小板減少症候群(SFTS)を含むダニ媒介感染症に関しては、ダニに咬まれないよう対策を行うとともに、もし発症した場合には、早期に医療機関を受診し、適切な治療を受けることが重要です。
マダニ
マダニは、固い外皮に覆われた比較的大型(種類にもよりますが、成ダニでは、吸血前で3~8ミリメートル、吸血後で10~20ミリメートル程度)のダニです。
※食品等に発生するコナダニや衣類や寝具に発生するヒョウダニなど、家庭内に生息するダニとは種類が異なります。
生息場所
鹿やイノシシ、野ウサギ等の野生生物が出没する環境に多く生息し、民家の裏山や裏庭、畑、あぜ道等にも生息しています。
主に森林や草地等の野外に生息し、市街地周辺でも見られ、日本全国に分布しています。
マダニが媒介する感染症
日本紅斑熱
潜伏期間は2~8日で、症状は高熱、発疹、刺し口等で、重症化し死亡することがあります。
主に西日本で発生が見られます。
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)
潜伏期間は6~14日で、症状は発熱、消化器症状等で、重症化し死亡することがあります。
2013年に国内で初めて患者が確認され、主に近畿・北陸地方以西で発生がみられます。
SFTSは、ウイルスを有するマダニに咬まれることにより感染しますが、今般、体調不良のネコに咬まれたヒトがSFTSを発症した事例が確認されました。
感染を防ぐためには、マダニに咬まれないように気を付けることや、動物との触れ合いについて注意することが重要です。
野生動物との接触は避けましょう。動物を飼育している場合、過剰な触れ合い(口移しでエサを与えたり、布団に入れて寝るなど)は控えてください。
飼い主自身が不調を感じたら、早めに医療機関を受診し、その際にペットの飼育状況や健康状態、動物との接触状況を医師に伝えてください。
また、屋内のみで飼育されているネコについては、SFTSウイルスに感染する心配はありません。
健康なネコなどからヒトがSFTSウイルスに感染することはないと考えられています。
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)について(厚生労働省のサイト)(外部リンク)
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)に関するQ&A(厚生労働省のサイト)
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)とは(国立感染症研究所のサイト)(外部リンク)
マダニから身を守るには
身を守る服装
農作業や庭仕事、レジャー等、野外で活動する際は、肌の露出を避けましょう。
- シャツの袖口は軍手や手袋の中に入れましょう。
- シャツの裾はズボンの中に入れましょう。
- 首にはタオルを巻くか、ハイネックのシャツを着用しましょう。
- ハイキングなどで山林に入る場合は、ズボンの裾に靴下をかぶせましょう。
- 農作業や草刈などではズボンの裾は長靴の中に入れましょう。
身を守る方法
- 虫避けスプレー(ディート、イカリジンなどの忌避剤)を噴霧しましょう。
- 野外活動後は、入浴や着替えをし、マダニが咬着していないか、チェックしましょう。
- ガムテープを使って服に付いたダニを取り除く方法も効果的です。
マダニに咬まれたら
マダニの多くは、ヒトや動物に取りつくと、皮膚にしっかりと口器を突き刺し、長時間(数日から、10日間以上のこともあります)吸血します。
マダニに咬まれても痛みがなく、気が付かない場合が多いと言われています。
吸血中のマダニに気がついたら
無理に取り除こうとするとマダニの口器が皮膚の中に残り、化膿することがありますので、医療機関(皮膚科等)で適切な処置(マダニの除去、洗浄など)を受けてください。
また、数週間程度は体調の変化に注意し、発熱等の症状が出た場合、医療機関で診察を受けてください。
その際はマダニに咬まれた又は疑いがあることを医師へ伝えてください。









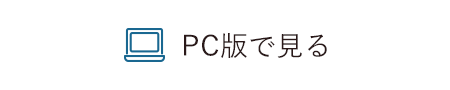
更新日:2025年04月01日