ノロウイルスや腸管出血性大腸菌感染症(O157等)による食中毒及び感染症等に注意しましょう!
ノロウイルス等による感染性胃腸炎に注意しましょう。
腸管出血性大腸菌感染症(O157等)に注意しましょう!
ノロウイルス感染症の特徴
ノロウイルスは手指や食品などを介して経口で感染し、人の腸管内で増殖します。感染力が強いため、特に注意が必要です。
主な症状
下痢、吐き気、おう吐、腹痛、発熱(39℃以下)
ウイルスが体内に取り込まれてから、通常24時間~48時間で発症します。(症状がなくても、便の中からウイルスが検出されることもあります。) 通常は1~3日で回復しますが、おう吐や下痢が続いた場合は脱水症状になることもありますので、早めに医療機関を受診しましょう。特に子どもや高齢の方は重篤化することがありますので、注意しましょう。
感染経路
(1)人からの感染
- 患者の便やおう吐物から人の手などを介して二次感染する場合
- 家庭や施設内などでの飛沫などにより感染する場合など
(2)食品からの感染
- 感染した人が調理などをして汚染された食品を食べた場合
- ウイルスの蓄積した、加熱不十分な二枚貝などを食べた場合など
感染が起こりやすい時期
ノロウイルスによる食中毒は一年を通じて発生していますが、特に冬季に多発する傾向があります。
予防方法
- 手洗いが一番の予防方法です
トイレ後はもちろん、調理前、食事前、おむつ交換後、吐物処理後などには、石けんを泡立てて十分な時間をかけて手洗いをしましょう。また、手洗い後に手を拭くタオルは清潔なものを使いましょう。 - 食品は内部まで十分に加熱しましょう!
中心温度が85℃、1分以上で十分に加熱しましょう。二枚貝などノロウイルス汚染が疑われる食品については、中心部が85~90℃、90秒以上で加熱するようにしましょう。 - 調理器具などの消毒には次亜塩素酸ナトリウム(市販の漂白剤など)や加熱(熱湯)が有効です。
- 下痢やおう吐などの症状があるときは、調理を控えましょう。
- 赤ちゃんに下痢症状がみられる時は、オムツを替えた後や沐浴後など、こまめに石けんで手を洗うようにしましょう。
- ノロウイルスは、食事以外でも感染することがあります。この季節におう吐や下痢があった場合は、ノロウイルスによる感染を疑い、おう吐物やふん便を処理する際は、ビニール手袋やマスクを着用しましょう。消毒剤を使用する際は、換気もしっかりと行いましょう。
ノロウイルスによる食中毒について(兵庫県のサイト)(外部リンク)
ノロウイルスに関するQ&A(厚生労働省のサイト)(外部リンク)
ノロウイルス感染症とは(国立感染症研究所のサイト)(外部リンク)

腸管出血性大腸菌感染症の特徴
家畜や人の腸内にも存在する大腸菌は、ほとんどのものが無害ですが、このうちいくつかのものは、下痢などを起こすものがあり、病原性大腸菌と呼ばれています。
その中には、ベロ毒素を産生し、出血を伴う腸炎や溶血性尿毒症症候群(HUS)を起こす腸管出血性大腸菌(O157の他にO26、O111など)と呼ばれるものがあります。
- 非常に少ない菌数で感染するため、感染力が強い!
- 大腸で増殖するときに毒素を産生する。
- 潜伏期間は、2~14日と長い。
主な症状
激しい腹痛と水様性下痢、血便(鮮血便)
発熱、吐き気、嘔吐などを併発する場合もあります。
症状のある方は、すみやかに医師の診察を受け、指示に従ってください。
感染経路
経口感染(菌に汚染された飲食物を食べることで感染したり、感染した人から人へ感染します)
感染が起こりやすい時期
食中毒は、気温が高くなる初夏から初秋にかけて発生しやすくなります。しかし、感染力が強い「腸管出血性大腸菌」は、他の食中毒に比べて気温の低い時期にも発生しています。
予防方法
- 生肉・ユッケは要注意!
特に、肉の生食は避けましょう。生肉に添えてあるサラダや野菜も、火を通してから食べましょう。 - 食品は内部まで十分に加熱しましょう!
中心温度が75℃、1分以上の加熱をしましょう。 - バーベキューや焼き肉、すき焼き等の時は、生肉に触れる箸と食事用の箸は別にしましょう。
- 調理前後、食事前、用便後は、必ず手を石けんでよく洗いましょう。
- タオルの共用はやめましょう。
- 調理器具は必ずよく洗い、塩素系消毒剤などで消毒しましょう。
- 赤ちゃんに下痢症状がみられる時は、オムツを替えた後や沐浴後など、こまめに石けんで手を洗うようにしましょう。
腸管出血性大腸菌(O157等)による感染症及び食中毒に注意してください!!(兵庫県のサイト)(外部リンク)
腸管出血性大腸菌感染症(O157等)に注意しましょう!









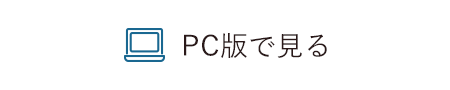
更新日:2025年04月01日