広渡廃寺跡歴史公園

昭和55(1980)年12月5日に国史跡指定
平成12(2000)年5月23日に「国史跡広渡廃寺跡歴史公園」としてオープン
広渡廃寺跡(こうどはいじあと)とは?
7世紀末頃に、地域の有力者を中心に建立された古代寺院跡です。平安時代終わりごろに失われ、寺の記録も無いことから、所在地の町名より「広渡廃寺跡」と呼ばれています。
昭和48(1973)年から同50(1975)年に発掘調査が実施され、奈良薬師寺と同じく、金堂前に東西両塔を置く、薬師寺式伽藍(がらん)配置であることが明らかとなっています。
ガイダンスホールの展示

広渡廃寺跡のことが一目でわかるように、寺の復元図、遺構整備図や出土品などを展示しています。
※ご覧になられる時は、各自でマスク着用等のコロナウイルス感染症防止策にご協力のほどお願いいたします。
基壇(きだん)の復元

寺の建物は、重い瓦を屋根にのせるため、柱が沈まないように土をつき固め、基壇という基礎をつくります。その上に礎石(そせき)という大きな石を置いて、柱を立てました。この基壇の外側には、平たい川原石を積んで化粧がなされています。
公園内には、この基壇を復元し、寺の配置や規模が一目でわかるようにしています。
金堂(こんどう)基壇

東西長約15m、南北長12.5m、高さ1.2mの長方形状の基壇の上に、本尊(ほんぞん)をまつるお堂が建っていました。基壇の外側は、平たい川原石で化粧の石積みがおこなわれています。
平安時代終わりには、基壇が西側へ3m拡張されて、一辺15mの方形の基壇となり、拡張部のみ瓦積みの化粧となっています。
広渡廃寺跡縮小伽藍(がらん)模型

往時の寺の姿を想像していただくために、屋外に縮尺1/20で伽藍模型を設置しています。日本で唯一のセラミックを用いた模型で、瓦一枚一枚、柱一本一本までていねいに復元したものです。


広渡廃寺跡歴史公園は、歴史学習の場、憩いの場として活用されています。









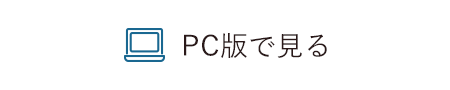
更新日:2023年04月27日