播州音頭
所在地:播州一円


播州音頭は、主として夏季に神社の境内や広場で夕方から夜を徹して行われる盆踊唱で、故人への供養として唄われるが、時には娯楽行事としても上演される。その起源は、文久年間(1861~1864)の頃より、美の郡吉川町で唄われていた吉川音頭である。明治30年代の頃、小野市天神町の岩崎鶴松(千鶴)、同山田町の岡田小兵衛(別品)、岡田佐衛門(流光)の3人が中心となり、吉川音頭内節調にクセ、クリ、ハギオトシタタキ等、いろいろな新工夫を加え、唄い始めたものが播州音頭とよばれるようになった。
なお、小野市市場町来迎寺境内の参道脇には、昭和4年に建立された播州音頭元祖記念碑がある。









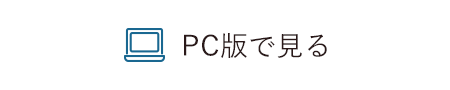
更新日:2022年01月17日